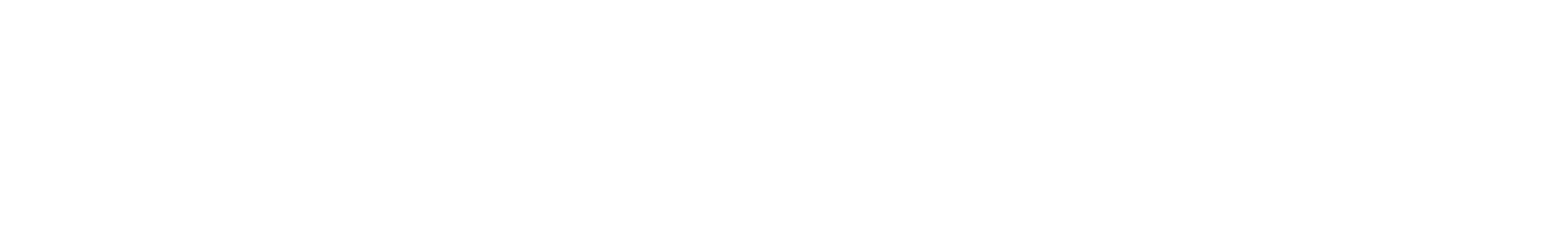想いを伝える適度な距離感
グループホーム「友」で世話人をさせて頂いている大原です。
社会福祉法人SHIPに入職して1年弱になります。
「友」は重度知的障がい者の方たちが共同生活を送る、あきる野市の施設です。

30代半ば頃まで、一般企業で人事職に就いていた私が、
福祉の世界へ転身するきっかけとなったのは、
複雑性・発達性トラウマ(幼少期の身近な養育者とのかかわりの中で生じたトラウマ)を
抱えるサバイバーと言われる方々を支援するNPO法人に、
ボランティアスタッフとして関わらせていただいたこと。
※トラウマサバイバーとは・・・
過去の心的外傷体験を生き延びた経験から、
現在に生きづらさを抱えている人たちのこと。
アダルトチルドレンという言葉が誤解を受けて
広まったことにより生まれた用語です。
自助グループの運営補助・精神科クリニックのデイナイトケアとの連携・
講演会の準備・電話相談などを通して精神医療の世界に触れ、
精神保健福祉士を目指して通信制の大学に通い始めたのですが、
学びを通した出会いの中で、少しの方向転換がありました。

知的に困難のある男の子を育てるお母さんと知り合い、
特別支援学校でボランティアをさせていただき、
実習先の児童デイサービス(現:放課後等デイサービス)で子どもたちと触れ合い・・・
※児童デイサービスは、さまざまな困難のある子どもたちが、
放課後や学校の休業日に通い、運動や創作等の体験を通して
生きる力をはぐくむ施設です。
そこで感じた居心地の良さがあり、精神保健福祉の世界に対する多少の違和感もあって、
実習先の施設でお仕事をさせていただきながら保育士の資格を取り、
自分はこの先、児童福祉に関わりながら生きていくのだと思っていたのに、
なぜか今は成人の方たちのグループホームで働いています(笑)
「様々な体験を通して生きる力を育てる」
ということを意識しながら、子どもたちとかかわる中で得たことは、
「利用者さんたちの自分でできる部分を増やす」
という「友」の理念に通じるものがあり、
今の仕事に活かすことが出来ていると感じています。

はじめての福祉の仕事で触れたことば、
「誰かの助けを受けながら生きることになるこの子たちには、愛される子になって欲しい」
今も大切にしている言葉なのですが、はてさて「愛される」とは・・・
子どもの育ちや、複雑性トラウマからの回復の世界で、
「子どもは周りの大人に愛されることで自分を愛し、人を愛するようになる」
というようなことが言われます。
では支援者として利用者さんたちを愛するとは?
利用者さんとの距離感は、近過ぎると共依存関係のようになり、
支援者は必要とされることに執心して、ご本人の自立をかえって妨げて
しまうことがある。
遠過ぎれば相手の存在を感覚でとらえることが出来ずに、
お定まりの関りに終始してしまう。
※共依存とは・・・
特定の相手との関係に対する過剰な依存。
相手に必要とされることへの過剰な執着。
依存されることに自分の価値を見出すさま。
相手に過剰に干渉して、自分に依存させることで、
相手の力を損ない、自立を妨げている状態。
それぞれの利用者さんにとって程よい構造化は、暮らしの助けになるけれど、
行き過ぎれば過保護になり、かえって相手を苦しめ、本来の力を損なうことにもなる。
※構造化は、自閉症等の障がいをお持ちの方が、
先の見通しを持てるように、環境や活動を
「視覚的」に分かりやすく整える方法。
こんな自問自答を繰り返しながら日々利用者さんたちと関わるのですが、
一つの答えを探しているわけではないのです。
繋がりの中で日々気付きを得て、関わりそのものを育て、自分自身の学びの糧としていく、
それが福祉の醍醐味であり、やはりこの世界とは離れられないなと感じる今日この頃です。
人に愛され、自分を愛し、人を愛する。
支援者として自分自身に真摯に向き合い、自分を大切にすること。
それが利用者さんたちを大切に想い、「愛」を伝えることになるのだと信じて、
日々寄り添い歩む日々を、このグループホームで送らせていただいています。