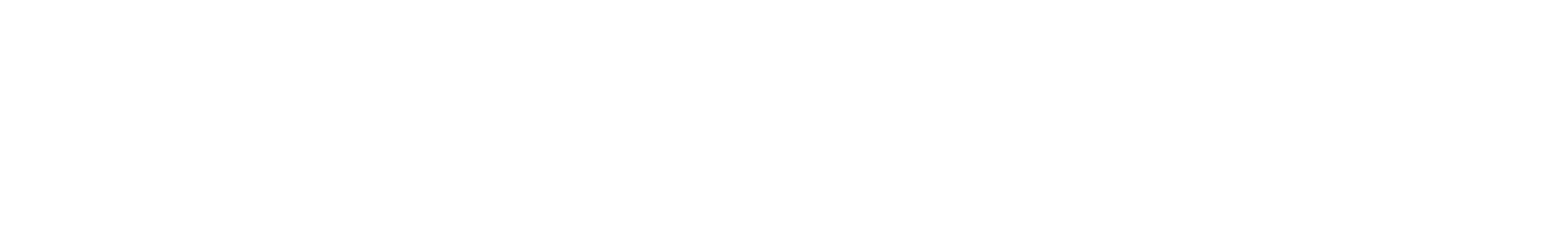感覚を数値化する
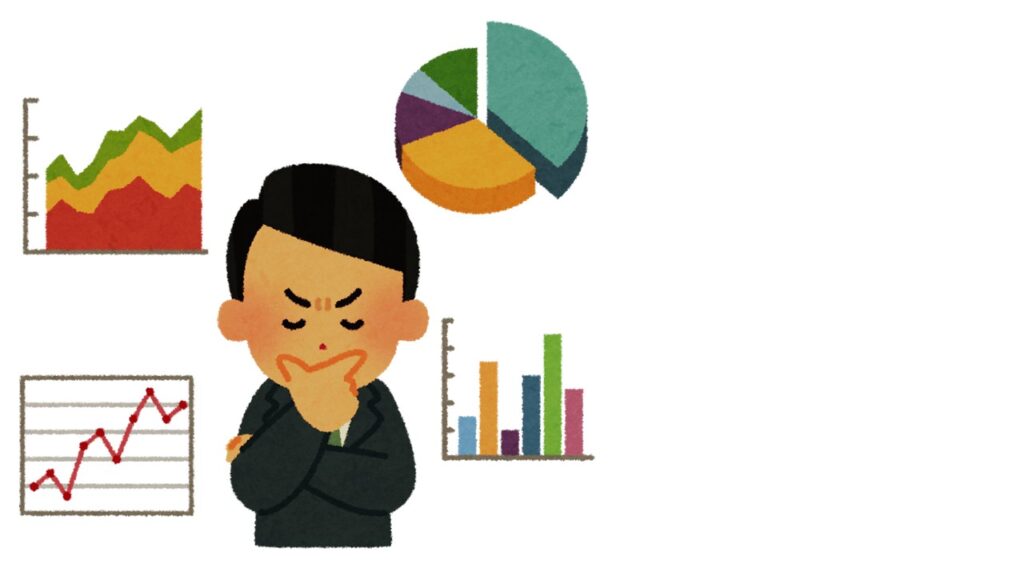
こんにちは。障害者グループホームに配属となり、今年の4月で3年目を迎えた石川一臣です。重度知的障害の方や自閉症スペクトラムの方々が多く暮らしており、日々職員同士協力しながら、安全と安心をモットーに入居者の暮らしを支えています。
最近、どんな仕事でも誰かに向けた何かがあるんだなと感じます。私は、対人支援や対人援助を職業にしており、人と人との関わりを通して繋がりや関係性を日々大切にしながら仕事に励んでいます。私は重度知的障害の方々の「その人らしい毎日」を作っていくことをテーマに、日々ご利用者様の支援に奮闘しています。
そんな奮闘の中、小さなすれ違いに気づきました。それは「感覚」をどう伝えるか、ということでした。特に重度の知的障害のある方の支援では、「感じること」や「伝えること」の小さなすれ違いが、不安や困惑につながることがあります。目に見えない「感覚」をどうすればスタッフ全員で共有できるのか、それが私たちの工夫のはじまりでした。
担当するご利用者様は、自閉症スペクトラムで重度知的障害を持っている方です。そのご利用者様はある日を境に夕食をだんだんと食べなくなりました。その為、体重もだんだんと減ってきてしまいました。
私は、職員に協力してもらい、食事の摂取量について報告をもらうことにしました。毎日「今日はあまり食べていない」とか「今日は良く食べました」とか「今日は食べたほうです」など、様々な報告をもらいました。当然、食べた量は人によって感じ方が違います。ニュアンスの違いはまさに感覚の小さなすれ違いを生み、共有を難しくしていることに気が付きました。そこで、実際に食べた量をパーセンテージで記録するようにしてみました。

すると、「〇〇さんは今日は70%食べたね」「最近はほとんど主菜を残してるね」など、曖昧だった情報が具体的な情報として報告を受けるようになりました。そうなると、具体的で客観的な情報となり、職員同士共有できるようになりました。こうして”感覚”を”数値”に置き換えることで、ご本人の体調の変化や好き嫌いの傾向といった見えないものが見えるようになってきました。
どんな仕事においても〝コツ″があると思います。その〝コツ″はいわゆる『経験と勘』と言われるものではないでしょうか。その『経験と勘』を具体的な言葉で、客観的な数値で表すことが出来れば、感覚のズレはなくなっていくのだと思います。ご利用者様も支援者も人間です。そのためそれぞれの感覚は持っていますし、当然人それぞれ違います。この違いが生む小さなすれ違いは、やがて大きな不安になるでしょうし、不利益を生むものではないでしょうか。
20年前に福祉に携わり始めたころ、先輩職員から漠然とした言葉で助言をもらっていましたが、よくわからないこと・上手く出来ないことが多くあったのを思い出します。なるべく具体的な言葉や数字で物事を伝えること、これは小さなすれ違いを防ぐための方法なのだと思います。支援者共通の認識や限りなく近い感覚を共有できないと、その不利益はご利用者様に返ります
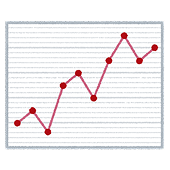
感覚を共有するのはとても大変ですが、福祉の現場においてはとても重要なことです。マニュアル通りに実施するのも大切ですが、現場にある曖昧な解釈を改めて具体化してみるのは重要なことです。これが20年に渡る私の福祉の経験と勘です。